今回は、「企業と幼稚園・小学校の類似性について ~ 組織の知性構成 と Yes 」 というテーマで考えてみます。
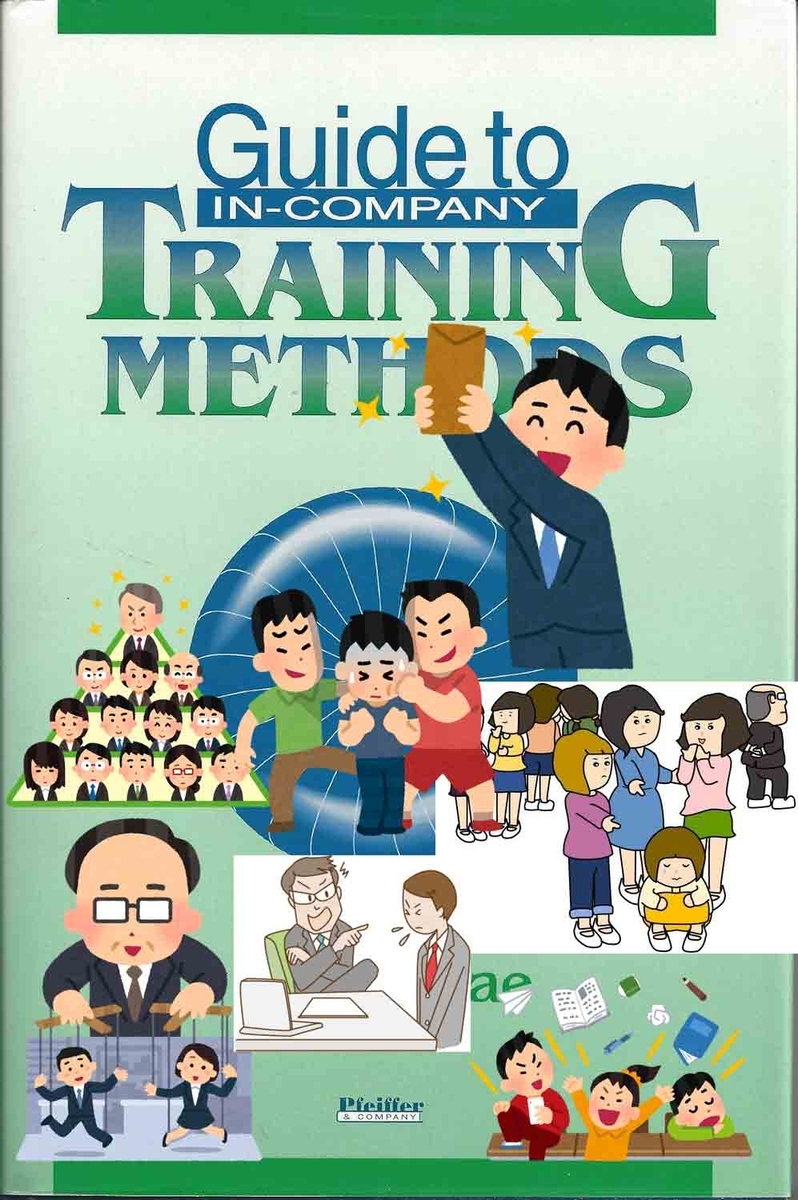
これまで2つの大企業といわれるような会社に属し、今は再雇用として、役職もボーナス(?)もなくなった身として、ふと考えると、大きな会社というのは、「幼稚園、小学校」にとても似ているところがあると思うのです。
それゆえに、「教育」が非常に困難になっているのではないか?
ということが、今回のテーマです。
「「企業」と「幼稚園、小学校」と何が似ている?」
のかというと、
” 組織の知性構成 ”
です。
「知性」というのは、経験することや学びによって変化、進化していくものだと思うので、「企業人」の「知性」が「幼稚園児」「小学生低学年」と同じだと言いたいわけではありません。
そうではなくて、
「知性の傾向の分布」
に類似性があるように思うのです。
人はなかなか一人では生き辛いので、経験を経るごとに「群れ」や「仲間」を作っていきます。そして、その「群れ」や「仲間」にはある程度自分に似ている人たちを選んで参加します。
「小学校高学年」→「中学生」→「高校生」
と、その傾向はどんどん強くなっていき、
究極の「群れ」や「仲間」は、「大学生」です。
勿論、大学でも「自分とは違う考えの人ばかり」というケースもあるでしょうが、多くの人が、その大学、学部、専攻を選択しているというのは、何かしら自分と近い部分や「知性」が似ているのではないか考えます。
その根拠として、「小学校」「中学校」である ” いじめ ” などが「高校」では少なくなり、「大学」ではほとんどなくなります(大学院や医局などの出世争いになると話は別です)。
勿論、その他多くの要因があることはわかっていますが、ある程度、自分と似た「知性」や「思考」を持った人間の集まりには、同じような組織の知性ベクトルができるように思われます。
ところが、それが、会社、特に大企業などに入った途端、
「こんな人間がいるなんて、、、」
「今まで、あんな人に会ったことがない、、、」
というようなことが多々あります。
それはそうです、会社というのはそれまでの自分の属していた「群れ」や「仲間」とは違って、「幼稚園、小学校」の時のように様々な「(経験、学びにより更に強化された)知性」や「考え」を持つ人々で構成されているからです。
そのため、「企業内教育」というのは難しいと思うのです。
最も簡単な(といっては怒られますが)、は「大学」での「教育」です。
同じような「知性」「思考」があり、更に「学ぶ分野」を専攻している。それに、前提の知識レベルが似通っている人たちなのですから、、、
また、もう一つ、「企業と幼稚園、小学校の類似性」があります。
それは、
「先生の命令には No と言えない」
ことです。
会社でも、どんなに「間違ったこと」でも「理不尽なこと」でも、上司からの命令に「 No 」とは言えません。
「幼稚園、小学校の生徒」は、条件反射的に「 Yes 」を選択しますが、「会社員」の場合には、本当は「 No 」だと思っていても選択肢は「 Yes 」しかありません、
「間違っていることは間違いだと言おう!」
みたいなビジネス書が何冊もありますが、それをやって会社で生き残れる人はほとんどいません。
そして、企業内の「教育」「研修」も基本的には上司もしくは会社からの命令によるものです(リスキリングなどいうモノは単なる戯言です)。
” やりたくないモノをやらせる、学びたくないモノを学ばせる、、、”
これが「企業内教育」の本質です。
まずは、その前提をよく認識して「教育デザイン」を考える必要があるわけです。
それには、何度も記しますが、やはりまずは効果的な「外発的動機づけ」を考える必要があり、” インセンティブ ” こそがその唯一の方略選択肢だと思うのです。
できるできないは、とりあえず保留しておいて、企業で「教育」「研修」をデザインする人は、そこから始まる、、、と思っていてもいいのではないでしょうか?