今回は、 ”「維持リハーサル (Maintenance Rehearsal)」と、「精緻化リハーサル(Elaborative Rehearsal)」 ” について整理し、少し考えてみます。
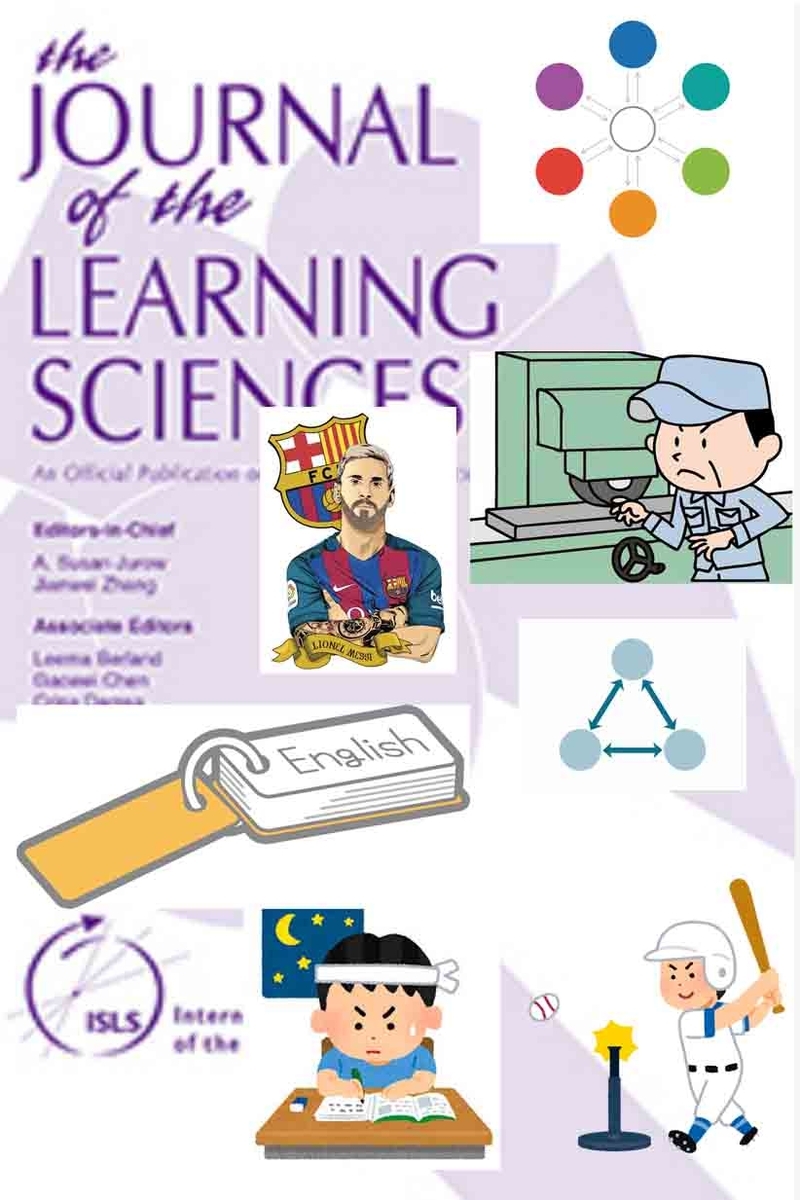
” リハーサル ” というのは、
短期記憶の忘却を防いだり、長期記憶に転送したりするために、記憶するべき項目を ” 意図的あるいは無意図的に ” 何回も反復して想起すること
です。
一般的には、リハーサルは「維持リハーサル (Maintenance Rehearsal)」と、「精緻化リハーサル(Elaborative Rehearsal)」の2つに分けられます。
(維持リハーサル:Maintenance Rehearsal)
短期記憶内に記憶を維持し、忘却を防ぐためのリハーサル。
同じ情報を単純に反復(単純な繰り返し)する。
短期記憶の保持に効果的。
情報の意味を深く理解することは求められない。
繰り返しによって記憶の保持時間が延長されるが、長期記憶に移行する可能性は低い。
(精緻化リハーサル:Elaborative Rehearsal)
統合的リハーサルとも呼ばれ、短期記憶から長期記憶に記憶を転送し、長期記憶の構造に統合するためのリハーサルである。
情報に対するイメージの構成や意味的処理によって、すでに獲得している情報と関連づける。
意味を考えたり、情報どうしを関連付けたりして覚える。
長期記憶の形成に効果的。
情報の意味を理解し、関連付けることが重要。
知識のネットワークを構築し、情報の検索が容易になる。
(比較と応用)
維持リハーサルは、短期的な情報の保持が必要な状況、例えば一時的に電話番号を覚える場合などに適している。
精緻化リハーサルは、学習や試験勉強、新しいスキルの習得など、情報を長期間にわたって保持し、理解する必要がある場合に適している。
(効果的な利用方法)
・維持リハーサル: 短期的なタスクや一時的な情報の保持に利用。リストを覚える、番号を一時的に記憶するなど。
・精緻化リハーサル: 深い学習や知識の定着を目指す。新しい概念を学ぶ際に、その概念を自分の言葉で説明したり、既存の知識と関連付けたりする。
(学習における” 精緻化リハーサル ”の有効性)
・深い理解
精緻化リハーサルは情報の意味を深く理解し、他の既存の知識と関連付けることを目的とし、学習内容が単なる記憶にとどまらず、理解として定着する。
・長期記憶の促進
情報を意味的に処理し、関連付けることで、情報は短期記憶から長期記憶に移行しやすくなり、学習内容が長期間保持されやすくなる。
・情報の検索性向上
関連付けが行われることで、情報のネットワークが構築され、必要な情報を検索しやすくなり、試験や実際の応用時に迅速かつ正確に情報を取り出すことができる。
・応用力の向上
深く理解された知識は、新しい状況や問題に応用する能力を高め、学習者は単なる暗記にとどまらず、創造的な問題解決能力を養うことができる。
(維持リハーサルの限界)
・短期間の記憶保持
維持リハーサルは短期間の情報保持には有効ですが、長期記憶には向いておらず、繰り返しの停止とともに情報が失われやすい。
・表面的な学習
情報を単に繰り返すだけでは、その意味や関連性を深く理解することが難しく、学習内容が表面的なものにとどまりがち。
(精緻化リハーサルの弱点)
・時間と労力がかかる
情報を深く理解し、既存の知識と関連付けるためのプロセスであるため、時間と労力が必要であり、短期間で大量の情報を覚えなければならない場合には効率的でない。
・事前知識の依存
新しい情報を既存の知識と関連付けることが基本であり、関連付けるべき既存の知識が不足している場合には効果が減少する。全く新しい分野の学習においては、関連付けが難しい。
・適切な関連付けの難しさ
情報を関連付ける際に、適切でない関連付けを行うと、誤った理解や混乱を招く可能性があり、関連付けの質が低いと、記憶の定着や検索が妨げられる。
・抽象的な情報の処理の難しさ
抽象的な概念や理論を精緻化リハーサルで処理することは、具体的な情報に比べて難しいことがある。抽象的な情報は具体例を見つけにくく、関連付けが困難になる場合がある。
・効果の個人差
個々の学習者の認知スタイルや既存の知識の違いによって、精緻化リハーサルの効果には個人差があり、ある人には効果的でも、別の人にはそうでない場合もある。
といったことです。
学習においては、常に「精緻化リハーサル(Elaborative Rehearsal)」が優遇(?)され、「維持リハーサル(Maintenance Rehearsal)」は、どちらかというと、” 無意味 ” であり、悪者(?)になっている感はあります。
理解、それも深い理解をするには「精緻化リハーサル(Elaborative Rehearsal)」が効果的であることは間違いがありません。
ライゲルースの「精緻化理論」はあっても、単純な記憶方法とも呼べる「維持理論」には誰も見向きもしません。
インストラクショナルデザインにおいても、「言語情報(記憶)」で留まるのではなく「知的技能(応用)」を養うことが重要ですし、単純な「記憶」は割と軽視されています。
しかし、英単語を何度も書いたり、単語カードで覚えようとする行為はムダではないと思うのです。例え短期記憶にしか効果がないと考えられていようと、
” 同じ情報を単純に反復(単純な繰り返し)する ”
という学習方略は、絶対的に必要だと思います。
野球でバッティングの練習をする際、すべてのスイングにおいて、関連性や情報を意識してバットを振っているでしょうか?
サッカーのパスをする際、単純に近くにいるチームメイトに向けて蹴りだしてはいないでしょうか?
「精緻化リハーサル(Elaborative Rehearsal)」というのは、既存の知識や情報が無ければ成り立ちません。つまり、後天的(?)というか、様々な知識、情報をインプットしてから、気づくモノです。
単純な記憶を求める「維持リハーサル(Maintenance Rehearsal)」の重要性を考えて執拗に実行し、やがてある分野においては「精緻化リハーサル(Elaborative Rehearsal)」を行っていくというのが ” 学習 ” であるように思います。