今回は、” 教育に「情報処理論的アプローチ」をとること ~ 自分自身の記憶の検索 ~ ” というテーマです。
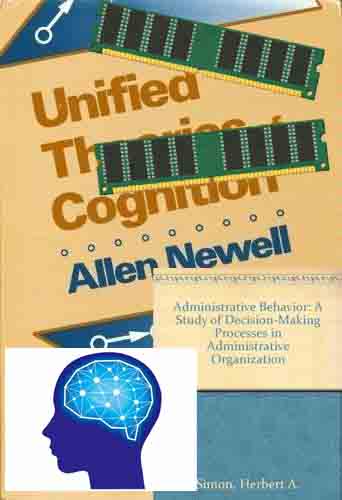
何度か記していますが「記憶」の話です。
何十年か前にこういった考えが提唱され、教育・学習の分野だけでなく、AI(ニューラルネットワーク等) の発展のベース知識に関与したことは間違いがありません。
そして、自分自身の記憶を ” 検索 ” して、” 強化 ” するため、と振り返りの意味もこめて、再度、この当たり前の、古い考えと教育・学習の周辺を考えてみます。
このブログは「備忘録」なので、「備忘録の備忘録」のようなモノです。
尚、「記憶」についての考えは、日々変わっていっていますので、自分が認知している基本的な部分についてのみ取り上げます。
(情報処理的アプローチ)
認知過程を情報処理という視点からモデル化し、そこから理論的に知的行動の個人差を説明しようとする。
人間の認知過程をコンピュータの情報処理に例えることで、行動と思考のプロセスを理解し、改善しようとする理論的枠組み。
(教育における「情報処理論的アプローチ」)
学習者の脳を情報を処理するシステムとして捉える
(記憶の構成要素)
・感覚記憶
外部からの情報が最初に入る場所で、非常に短い時間しか保持されない。
・短期記憶(作業記憶)
情報が一時的に保持され、処理される場所。情報の保持時間は短く、容量も限られている。
・長期記憶
長期間にわたって情報が保存される場所で、容量はほぼ無限。
(学習のプロセス)
情報がどのようにして感覚記憶から短期記憶、長期記憶に移行するかのステップ。
・注意
感覚記憶に入った情報の一部が、注意を引くことで短期記憶に移行。
・符号化
短期記憶に入った情報が、理解しやすい形に変換され、情報を意味的に関連付けたり、イメージ化することが含まれる。
・貯蔵
符号化された情報が長期記憶に保存。
・検索
必要な時に長期記憶から情報を取り出し、短期記憶に再度持ってくるプロセス。
(教育への適用)
・効果的な授業デザイン
情報が効率よく符号化され、長期記憶に保存されるような授業デザインを考えることが重要。マルチメディア教材を利用して視覚と聴覚を同時に刺激する方法など。
・復習と練習
情報を長期記憶に定着させるためには、繰り返しの復習と練習が必要。スパイシング法(間隔を空けた復習)などが効果的。
・メタ認知の促進
学習者が自分の学習プロセスを意識し、制御できるようにするための指導が重要。目標設定、計画、自己評価など。
と、現在ではほぼ「常識」としてとらえられている考えですが、ハントやスターンバーグが世に出した頃には、恐らく非難の声も多くあったのではないかと思います。
その後、教育・学習の分野では様々な方略が考えられ、現在もそれは続けられています。
(教育・学習方略)
・有意義な符号化を促進する方略
>前知識の活用
新しい情報を既存の知識と関連付けることで、理解しやすくなる。先行オーガナイザー(新しい内容を学ぶ前に提供される概要や枠組み)を使用する方法が含まれる。
>具体例の使用
抽象的な概念を具体的な例や物語に変換することで、学習者が情報をより深く理解できる。
>視覚的教材の利用
グラフィックオーガナイザー(マインドマップ、フローチャートなど)やイラスト、図表を用いることで、情報の視覚的な理解を促進。
・作業記憶の負荷を軽減する方略
>情報のチャンク化
大量の情報を小さなまとまり(チャンク)に分けることで、作業記憶の負荷を軽減。電話番号を3桁ずつ区切って覚える方法等。
>ステップバイステップの指示
複雑な課題を段階的に分けて指示することで、学習者が一度に処理しなければならない情報量を減らす。
>自動化の促進
基本的なスキルや知識を反復練習によって自動化することで、作業記憶の負荷を減らし、より高度な認知活動に集中できるようにする。
・長期記憶への定着を促進する方略
>反復学習
繰り返し学習することで、情報を長期記憶に定着。スパイシング(間隔を空けた復習)や累積復習(以前に学んだ内容を再度取り入れる)などの方法も効果的。
>テスト効果の利用
自己テストやクイズを行うことで、情報の検索と再符号化を促進し、記憶の定着を助ける。
>自己説明
学習者自身が学んだ内容を自分の言葉で説明することで、理解を深め、記憶の定着を助ける。
・メタ認知を促進する方略
>自己監視と自己評価
学習者が自分の理解度や学習進捗を定期的にチェックし、必要に応じて学習方法を調整する習慣を身につけることが重要。
>目標設定と計画
学習者が具体的な学習目標を設定し、それに向かって計画的に学習することを支援。
>フィードバックの提供
学習者が自分の進捗や理解度について適切なフィードバックを受けることで、自己調整能力を高める。
・学習環境の最適化
>集中できる環境の整備
学習に集中しやすい環境を整えることが重要。静かな場所、適切な照明、快適な座席などが含まれる。
>デジタルツールの活用
学習管理システム(LMS)や教育用アプリケーションを用いて、学習の進行状況を管理し、必要なリソースにアクセスしやすくする。
などなど、、、ですね。
現在は、このような考えのベクトルで物事のすべてが進んでいますが、もし、全く違った考えが出てくる可能性もないとはいえません。